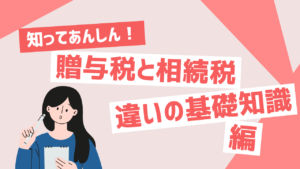自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると紙とペンさえあれば気軽に作ることができる反面、偽造や破棄、紛失のおそれがあります。また、相続手続きが始まると検認の手続きが必要となり少し手間がかかってしまうというデメリットもあります。
これらのデメリットを解決するために自筆証書遺言を利用しやすくするという趣旨で、令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度というものが始まりました。
ここで、制度の概要について把握しておきましょう。
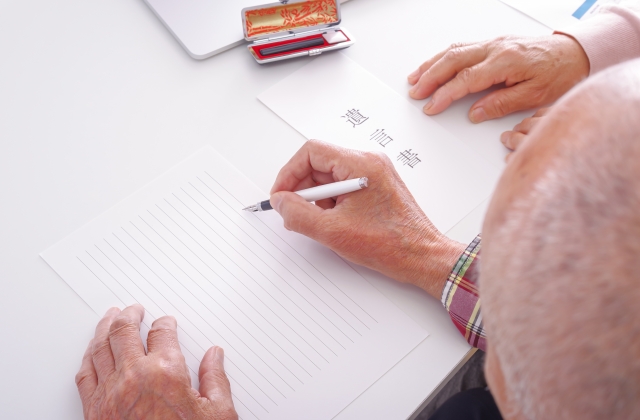
自筆証書遺言書保管制申請方法
自筆証書遺言を作成したら、法務局(以下遺言書保管所という)に遺言書の保管申請を行います。
この申請は遺言書を作成した本人が行う必要があり、家族や代理人、使者が行うことは認められていません。また電話予約が必要ですので予め電話で予約をしておきましょう。
自筆証書遺言書の保管と閲覧
自筆証書遺言書の原本は遺言書保管所で保管されます。災害などの滅失のおそれを考慮してデータでも保管されるので安心です。
遺言者は遺言書保管所に行きいつでも遺言書の閲覧を請求することができますが、遺言者が存命中は、遺言者以外の推定相続人などは閲覧することはできません。
遺言者の死亡後

遺言者が死亡した後は、誰でも遺言保管所に「遺言保管事実証明書」の交付を請求することで、自分が相続人や受遺者になっている遺言書が保管されているか確認することができます。また、相続人は遺言書の写し(遺言書情報証明書)の交付も受けられます。
遺言書の写しが請求されたり、遺言書の閲覧が行われた場合、法務局は他の相続人などの関係者に対して遺言書が保管されていることを通知します。
このような手続きを行うことにより家庭裁判所の検認手続きは不要とされているため、スムーズに相続手続きを行うことができるようになります。
遺言者が指定した方への通知(指定者通知)
遺言者の死亡後、関係相続人等が遺言書の閲覧や遺言情報証明書の交付を受けると、関係相続人に通知が届きますが、逆に閲覧や交付請求がされないと通知が実施されません。
その対策として、遺言者が希望する場合には別の通知制度も用意されています。
その方法とは戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方(3名まで指定可)に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。使い方によってはとても便利な制度となっています。

自筆証書遺言の申請方法
| 申請できる人 | 遺言者のみ |
| 申請する遺言書保管所 | ①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者所有の不動産所在地 |
| 申請に必要な費用 | 1件につき3,900円 |
| 必要なもの | 申請書、本人確認書類、封をしていない自筆証書遺言、本籍の記載がある住民票の写し など |
自筆証書遺言書保管の手数料一覧
| 申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
| 遺言書の保管申請 | 遺言者 | 3,900円/1件 |
| 遺言書の閲覧請求(モニター) | 遺言者、関係相続人 | 1,400円/1回 |
| 遺言書の閲覧請求(原本) | 遺言者、関係相続人 | 1,700円/1回 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人 | 1,400円/1通 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人 | 800円/1通 |
| 申請書等・撤回書等の閲覧請求 | 遺言者、関係相続人 | 1,700円/一の申請書等・撤回書等 |